こんにちは、Dr.シェパードです。
健康診断などでも検査されることのある、ヘリコバクター・ピロリ菌(Helicobacter pylori)。一般の方にはまだまだ馴染みが無いかもしれないですが、日本人にとって切っても切れない関係にあります。
家族で陽性の人がいた、人間ドックや健康診断で受けた検査で陽性といわれた、ABC検診を受けてみた、はたまた胃潰瘍や十二指腸潰瘍になったなどいろいろな場面で一度は聞いたことがあるかもしれません。
 Dr.シェパード
Dr.シェパード私は胃カメラをうけて調べた結果ピロリ菌の感染はなかったです。



私も胃カメラをうけてピロリ菌の感染はありませんでした。昔に川の水を飲んでしまったことがあって心配でした。
そんなヘリコバクター・ピロリ菌(Helicobacter pylori:以下”ピロリ菌”)について詳しく説明していきます。
ポイント
- ピロリ菌は乳幼児期にすでに感染している可能性がある、強酸性の胃の中で生き続けることのできる菌である
- ピロリ菌が居続けると胃がんなど命に関わる疾患や様々な疾患のリスクとなりうる
- 発見する検査には内視鏡を使う方法と使わない方法があるが、結局胃カメラ検査は必須である
- ピロリ菌の除菌治療の基本は内服薬3種類を1週間飲むだけであるが100%成功するわけではない(アレルギーなど副作用が出た場合には必ず医療機関に相談を)
- 除菌治療終了後の4週以降に除菌判定を必ず行う
- 除菌治療に成功しても不成功でも1-2年に1回の胃カメラ検査が推奨される
ヘリコバクター・ピロリ菌とは
ヘリコバクター・ピロリ菌が発見されたのは1982年のことです。意外と最近のことですよね。オーストラリアの後にノーベル医学・生理学賞を受賞する、ウォーレンとマーシャルという2人の医師により発見されました。元々はその100年程前から胃の中に細菌がいるという説がありましたが、胃の中の強い酸性条件で生きられる細菌はいないという説が強かったのです。
胃炎を起こした胃粘膜にらせん型の細菌がいることを発見したウォーレンはマーシャルとともにこの細菌の存在を証明するために研究しました。それまで見つからなかった原因はこのピロリ菌の培養が非常に時間がかかることが原因で、通常4日程要するためそれまでに諦められてしまっていたのです。たまたまイースター祭のために放置していた培地で培養されたことで発見されたのがこのピロリ菌でした。



名前はヘリコが「らせん」、バクターは「細菌」、ピロリは「胃の幽門」で発見されることが多かったことから名付けられました。
なぜ、強酸の胃の環境で生きられるのかと言うと、「ウレアーゼ」という酵素を産生し、胃液中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解することで生じたアンモニアで胃酸を局所的に中和することで生き続けています。
感染経路は
詳細な経路は不明ですが、胃内に定着するため経口感染すると考えられています。口から口、糞から口感染が想定されています。保菌している親と胃酸が弱い小児期での濃密な接触(離乳食の口移しなど)、糞便に汚染された水や食品を介した感染が考えられています。
最近の日本の水質環境ではあまり生水を飲んで感染するということはないため、乳幼児期での接触が原因かもしれません。
生活環境の変化、育児の変化もあるのか20代などの若年世代でのピロリ菌の有病率はどんどん減っています。
問題となる病気は
一番イメージしやすいリスクとなる病気は胃癌です。ヘリコバクター・ピロリ菌が感染した胃では慢性的に炎症が起こりダメージを受け続けることとなります(慢性胃炎・萎縮性胃炎)。それにより将来的に癌になる可能性が出てきます。また軽微なダメージであれば胃潰瘍や十二指腸潰瘍といった消化性潰瘍も起こします。軽度であってもヘリコバクター・ピロリ関連ディスペプシア(HpD)という機能性ディスペプシア(FD)の亜分類として食後のもたれ感、早期膨満感、心窩部痛、心窩部灼熱感などの症状を呈することもあります。
実際にピロリ菌の除菌治療が始まってから日本人の胃がんによる死亡率は激減しました。また、韓国の研究では胃がんの家族歴がある患者でヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療により胃がんリスクの低下につながったことが示されました(IJ Choi. NEJM. 2020; 382(5): 427-436)。
これらは直接的に胃へのダメージの結果としてイメージしやすいのですが、不思議なことにMALTリンパ腫やびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)といった血液に関連した疾患の原因にもなることがわかっています。また慢性蕁麻疹や小児の鉄欠乏性貧血などの原因となることも考えられています。
命に関わる疾患のリスクとなることから、その治療をすることは重要となります。
自力でできる癌予防の数少ない一つです。
日本では保険適応で治療ができ、その対象は上記のうち
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療中または既往がある
- 胃MALTリンパ腫
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 早期胃がんの内視鏡治療後、内視鏡検査でピロリ関連の胃炎と診断された
いずれかに当てはまる場合です。
検査方法
検査方法には大きく分けると内視鏡を使う方法と使わない方法があります。
内視鏡を使わない
- ヘリコバクター・ピロリ抗体検査(採血):簡便であるが、既感染かどうかしかわからないため除菌判定に使えない。偽陽性に注意が必要。
- 尿素呼気試験(呼吸のみ):簡便であり現感染かどうかわかるため除菌判定にも使用可能。検査前準備で注意が多い。
- 便中抗原検査(便検査):便検査自体に抵抗があることが多い。除菌判定にも使用可能。
内視鏡を使う:胃の一部を採取(生検)して検査
- 迅速ウレアーゼ試験:簡便
- 鏡検:時間がかかる
- 培養:時間がかかる
内視鏡検査で行う場合は迅速ウレアーゼ試験が最も多いと思います。



内視鏡を使わなくていいならやりたくない・・・その気持ちはわかりますが、使わない方法で陽性だったからと行って安易に治療を行わないように学会から注意が来ています。また本来は内視鏡検査でピロリ菌感染が疑われる場合に初めて存在の検査を行うことが要件となっていますし、年齢が高ければ癌のリスクもありますから嫌かもしれませんが自分のために受けましょう。
ちなみに上に書いたABC検診とは胃がんリスク検査のことで、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査とペプシノーゲン検査を組み合わせて判定するものになります。
ペプシノーゲン検査はピロリ菌による胃へのダメージにより萎縮性胃炎が起こりそれに伴いペプシノーゲンの産生が低下することを利用して陽性(産生低下状態)を判定しています。どちらも陰性であればA群で胃がんリスクが極めて低い、ピロリ抗体陽性・ペプシノーゲン陰性はB群で感染初期の可能性、ピロリ抗体とペプシノーゲン陽性はC群で胃がん発症リスクが高く、ピロリ抗体陰性・ペプシノーゲン陽性はD群で萎縮が進みきった状態の可能性があり胃がんリスクが非常に高いという分け方になります。時系列を考えるとわかりやすいですね。
治療方法
執筆現在は3つの薬による内服治療を1週間行う除菌治療が主流です。非常に簡便で気軽にできますのでご安心ください。また保険適応は2回目の治療: 2次治療までで、3次治療以降は自費診療となり成功率がやや下がります。
構成としては胃酸を抑える薬1つと抗生物質2つを組み合わせたものになります。内服を始めたら必ず飲みきり、後ほど書いた重篤な副作用がない限り途中でやめないでください。
実際の治療についてですがボノプラザン(P-CAB)の登場後はボノプラザンを用いた内服治療がPPIを用いた治療より除菌成功率が高いことがわかっており、現在は主流となっています。


除菌治療
- 1次治療:ボノプラザン(P-CAB)またはPPI+クラリスロマイシン(CAM: 抗生物質)+アンピシシリン(AMPC: 抗生物質)
- 2次治療:ボノプラザン(P-CAB)またはPPI+メトロニダゾール(MNZ: 抗生物質)+アンピシシリン(AMPC: 抗生物質)
- 3次治療:ボノプラザン(P-CAB)またはPPI+レボフロキサシン(LVFX: 抗生物質)またはシタフロキサシン(SFTX: 抗生物質)+アンピシシリン(AMPC: 抗生物質)
ボノプラザン使用の場合の成功率は、1次治療としては報告上からおよそ85%-90%前後ほどで2次治療のメトロニダゾールを使用した治療では85-95%程とされるが報告によりまちまちといった印象で、3次治療に至っては75-80%程といったところです(Shu Kiyotoki. Intern Med. 2020; 59(2): 153-161)。
また、報告である程度ですが乳酸菌製剤の併用は副作用リスクを減らし除菌成功率を上げるとの報告もあり(Goran Hauser. Medicine(Baltimore). 2015; 94(17): e685)、乳酸菌製剤による副作用があまりないことから私は耐性乳酸菌製剤の処方を同時に行っています。
副作用で多いのは消化器症状で特に下痢は目立つ印象です。他にも上腹部痛、嘔気などの症状が見られる方もいます。しかしおよそが飲みきり終了すれば改善することが多い印象でやめてしまうことで除菌が不成功に終わるデメリットとのほうが大きいとも考えます。
一方で必ず内服を中断すべき症状がアレルギーによる蕁麻疹や皮疹などです。この場合は内服を続けてしまうと悪化し、最悪の場合死に至る危険性もありますので内服の中止をしつつ、処方された医療機関へ相談をしましょう。
除菌治療は100%成功するわけではありませんから必ず除菌判定検査が必要です。一方で除菌治療直後に判定をしてしまうと、仮に失敗していた場合でも一時的に減った菌により判定検査が偽陰性となってしまう可能性がありますので、終了後4週以降に上記の尿素呼気試験や便中抗原検査で行います。
除菌治療のあとは
無事にピロリ菌の除菌ができたとしても安心してはいけません。なぜなら、先述の通りヘリコバクター・ピロリ菌は乳幼児期に体内に入ってくると考えられています。つまり成人になり見つかった場合にはピロリ菌によるダメージを少なくとも10年は受けているのです。それにより、一生涯で2人に1人が癌になると言われているなかでダメージを何年も受けた胃で癌ができなくなるなんてことはありません。むしろピロリ菌がいないで過ごした人より癌が発生するリスクが高いのは当然です。ただ、ずーーっとダメージを受け続けるよりある時点でダメージをストップしたほうが確率が下がるのは確かですので無駄というわけではありません。
いつ癌ができるかわからないのは他臓器も同じですが、すでにリスクを負った胃に関しては細かく見たほうが安心では無いでしょうか?
基本的には除菌治療後も1-2年に1回の胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)を推奨しています。また除菌治療が不成功に終わった方も同様のスパンでのフォローアップが必要です。
せっかくピロリ菌を治療したのですから胃がんが進行して大きい手術をすることになる前に内視鏡で負担が少なく治療できるうちに見つけるのが一番です。
最後に
日本人ときっては切れない関係にあるヘリコバクター・ピロリ菌について解説しました。
ふとした拍子に聞いたことがあるけれどもよく知らかなった方、健康診断や人間ドックで突然陽性と言われたからどうしようと不安になられた方などの参考になりましたでしょうか。
また若手の先生方の少しでも参考になれば幸いです。
ヘリコバクター・ピロリ菌の治療を行い、将来の胃がんなど命に関わる疾患の予防を行っていきましょう。
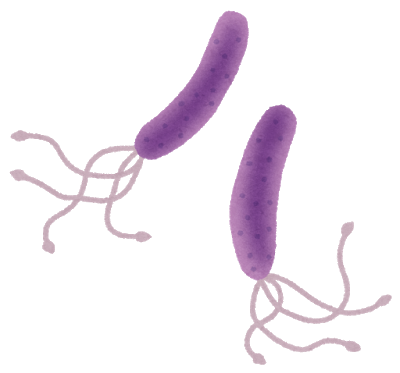





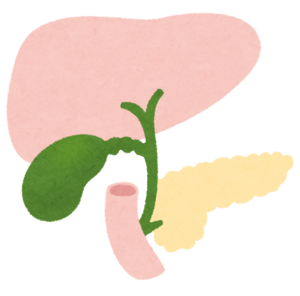
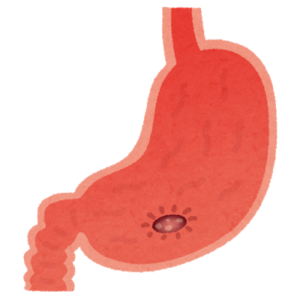
コメント